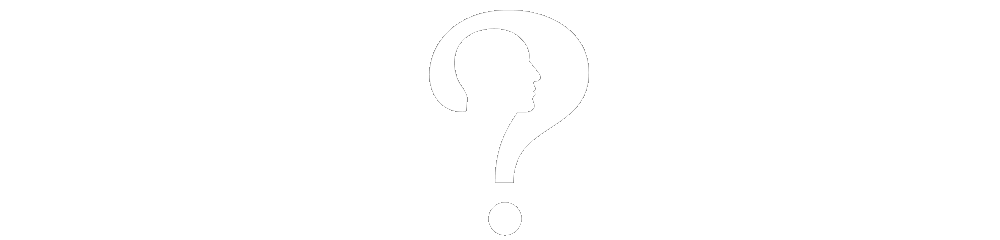マジックの世界において、特にマジシャンの間では、種明かしはタブー視されています。しかし、テレビ・YouTube・TikTokなどの媒体で、種明かしが広く行われているのも事実です。そして、種明かしはしばしば議論の的となってきました1 2。この記事では、種明かしがタブー視される理由、種明かしに対する賛否、マジックの種を保護する方法、当サイトの立場をまとめたいと思います。
否定派:マジックの種明かしをタブー視する理由
マジックの価値を維持するため
種は不思議さの核心
マジックの種明かしをすると、不思議さという価値が失われるのが理由として挙げられます。マジックが不思議な現象として目に映るのは、種が秘匿されているからです。不思議の定義は「どうしてなのか、普通では考えも想像もできないこと。説明のつかないこと。また、そのさま。」とされています 3 。種明かしは、マジックを説明のつくありふれた現象にすることなので、マジックの特長である不思議さは失われることになります。
サーストンの三原則
マジシャンの間では、サーストンの三原則と呼ばれるルールが知られています。マジックを不思議に見せるために重要な原則です。サーストンの三原則は以下の3つから構成されており、その中に「種明かしをしてはいけない」というルールがあります 4。
- 披露する前に現象を説明してはいけない
- 繰り返してはいけない
- 種明かしをしてはいけない
観客を幻滅させる
種明かしによって、不思議だな、と楽しんでいた気持ちが冷めてしまうことがあります。マジックを楽しんでいらっしゃる方の中には、不思議な現象を体験したいからマジックの種は知りたくない、と考える方がいます。こうした方々に種明かしをするのは、楽しみを奪うことになります。
マジックの価値の低下
特に、無料で種明かしをする場合に起こる問題です。不特定多数の人が、何のコストも支払わずに、簡単に種を知ることのできる状況は、「マジックやマジックの種には何の価値も無い」、「マジックは種さえ分かれば誰でもできる」、といった誤解を生みかねません。1つのマジックの裏には多くの創意工夫があるのですが、軽々しく扱われているものを、価値あるものだと認識するのは難しいでしょう。
権利を保護するため
知的財産権の侵害
マジックのクリエイターが特許等を取得している場合、安易な模倣や種明かしは知的財産権5 を侵害するおそれがあります。例えば、マジックメーカーのテンヨーのように自社製品の特許6を取得している企業の商品を模倣して種明かしすれば、権利侵害を主張されるでしょう。また、ペン&テラー(Penn & Teller)のTeller 氏7が、特許取得済みの自身の演技を、他のマジシャンに模倣されて販売された件で訴訟し、この裁判に勝利したという事例もあります8。特に、営利目的で模倣された商品の中で種明かしが行われる場合に、こうした問題が起きるようです。
クリエイターの搾取
マジックの種の開発に多大な貢献をしているのはクリエイター(考案者)でしょう。しかし、自分の作ったマジックの種を次々に公開され、紹介者やプラットフォームの運営者ばかりが利益を受け取るのであれば、クリエイターは搾取されることになります9。お金のためだけにマジックをしているわけではなくても、お金が必要ないわけではありません。自身の成果物に対価が支払われず、貢献度の低い他人ばかりが利益を得る状態が続けば、創作意欲は削がれ、やがて文化は衰退します。
持ちネタを奪う
種明かしにより、パフォーマーの持ちネタに制約をかけ、営業上の自由を奪ってしまう問題もあります。種が単純でも優れたマジックはあります。それらは、演じる負担が小さく効果が高いため、自身のレパートリーに取り入れているプロもいます。ですので、単純な種だからといって詳らかに種明かししてしまうと、種が知られたために使いづらくなってしまうマジックを増やしてしまうことになります。
道義的に問題があるから
他者の成果物の剽窃
端的に言えば、他者が多大な労力を費やして考案したマジックを、第三者が勝手に種明かしすることは、他者の成果物を盗んでいるようなものだという主張です。クリエイターが考案したマジックを、第三者が種明かしして、第三者しか利益を得られない構造は不公平に思われます。
迷惑行為につながる
種明かしは「種を知っている」という冷やかしの原因になります。こうした冷やかしは、種が正しいかどうかとは関係なく、ファンタジーを楽しみたい人を現実に引き戻したり、楽しませようとしている演者の妨げになったりします。また、このような迷惑行為の増加に伴い、迷惑行為が許されるという認識が広まることも危惧されます。
肯定派:種明かしを容認する理由
そもそも問題が無いする立場
種明かしは一般的である
現状として、種明かしは広く行われています。例えば、書籍、DVD、講習会、オンラインコース、マジックグッズなどが挙げられるでしょう。賛否はさておき、近年ではYouTubeやTikTokといった媒体でも種明かしが行われるようになりました。
法律上の規制は無い
一般に、マジックの種そのものは著作物ではありません10。また、種明かしによってマジシャンが損害を被るという主張も法的には認められないようです11。特許を取得している場合などを除き、種明かしをしただけで法的責任を問うのは難しいと考えられます。
マジックの文化が発展するから
マジックの伝承
マジックを演じる上で種を理解することは必須です。演じ方が分からなければ、そのマジックは誰も演じることができなくなります。ですので、マジックの種明かしは、過去のマジックが次の世代へと継承され、マジックの文化が維持されるためには必要だといえます。
マジック人口が増える
種明かしがある方が、より視聴者の興味を惹くので、マジックに触れる人が増えるだろう、という主張です。実際に、メディア運営者として、種明かしを求めて検索する人が多いことも把握しています。ほとんどのマジシャンは、何らかの種明かしを見て、マジックを始めたでしょうから、種明かしがきっかけでマジックの世界に足を踏み入れる人はいると思います。
マジックの面白さが伝わるから
ここでの面白さとは、不思議さというよりは、知的欲求の満足の意味合いが強いです。マジックについて本格的に話をしようと思うと、核心である種の部分を避けるわけにはいきません。そのトリックに詰め込まれた考案者の創意工夫、トリックの存在を隠しつつ魔法を演出するための演技構成などは、種を抜きにしては語れないでしょう。
透明性の確保
考案者と出典を明らかにして種明かしを行うことは、透明性の確保に繋がります。マジックに関する情報が、客観的に検証可能で、信頼性の高いものになるということです。もっとも、マジックには秘密を隠そうとする性質があり、閉鎖的になりがちなので、透明性の概念とは相容れないかもしれません。一方で、こうした秘密主義的な性格が災いし、既知のアイディアの不要な再発見、自称オリジナル作品の乱立、考案者の特定不能とそれに乗じた海賊版の横行、購入しないと中身が判断できない不透明さ、といった数多の問題を引き起こしているともいえます。
商業的なメリットがあるから
金銭的な利益が得られる
現実的な話として、金銭的な利益が得られるのは重要です。クリエイターやマジックショップなどは、自身の創作したマジックの種明かしをすることで利益を得ています。是非はともかく、他人のマジックを種明かしすることで、自身が広告収入を得られるという現状も、種明かしを後押ししているでしょう。
広告効果が高まる
テレビなどのマスメディア、YouTubeなどのSNSでは、広告業という形態上、多くの人の目に触れることが重要です。種明かしを行う方が、再生回数や視聴回数が伸び、広告効果が高くなるのであれば、法律ではない倫理観など無視して、営業利益を最大化するのが合理的でしょう。
顧客の知的好奇心を満足させる
マジックを見て「なぜ?」という考えが出てくれば、マジックの種を知りたくなるのは理解できます。種明かしをすれば、こうした疑問に答えが与えられ、知的好奇心が満たされます。ビジネスとしては、顧客のニーズが存在する以上、それに応えるのが正解なのかもしれません。ただ、こうした顧客が求めているのは、マジックの不思議さというよりも、クイズのような面白さなのかもしれません。
自身の満足感のため
過去の種明かし行為の正当化
マジシャンが、自身の過去の種明かし行為を咎められたくないという心理もあると思います。種明かしをすべきではないと主張し、後ろめたく思いながらも、様々な理由で種明かしをしてしまうことはあります。その後、言動の一貫性を保とうとすると、ある程度までは種明かしを容認せざるを得ないことになります。
優越感に浸れる
種明かしをすると、他人が知らないことを自分だけが知っているという優越感に浸れます。マジシャンだけでなく、YouTuber や観客にも、このような欲求から種明かしを行う人はいます。例えば、YouTuberであれば、種明かしをして「凄い」と言われると承認欲求が満たされるでしょう。観客であれば、演技中に「それ知ってる」などと声高に叫べば、自分は他人に騙されない聡明な人間だと示せるのかもしれません。
マジックを種明かしから守る方法
法律による保護
個人では非現実的ですが、法人ならば知的財産権を取得して保護することは考えられます。演技のルーティーンであれば著作権による保護も可能かもしれません。ただし、知的財産権による保護は、保護対象を明確にする必要があり、種を隠して保護したいにもかかわらず、種を公開しなければならないというジレンマを抱えることになります。
秘密保持契約(NDA)
マジックの種を教える相手に対して、利用規約や秘密保持契約(non-disclosure agreement:NDA)などで種明かしをしないことに同意させる方法があります。もちろん、完全に契約が履行される保証はないので、違反した場合には、違約金や損害賠償を請求するといった措置も取れるようにします。
観覧に条件をつける
パフォーマーの方などは、演技の種明かしをしないことに同意した場合にのみ、ショーの観覧を許可するという方法もあります。仮に契約を反故にされた場合には、営業妨害であると主張したり、次回以降の出演をお断りしたりすることになります。
ペイウォール(Pay Wall)
有料にすることで、情報の公開範囲に制限をかけることです。お金を払う(Pay)ことが情報流出の障壁(Wall)になっています。マジックグッズ、書籍、DVDなどもある種のペイウォールといえるでしょう。一方で、マジックの業界では、過度に情報を秘匿して、価値判断が難しくなることもあるので、バランスを取ることが重要です。
教える相手を選ぶ
いくら正論を並べたところで、無料で種明かしすることを要求し、秘密や約束を守らず、自分さえ得すれば良いという考えの人は存在します。一方で、物事の価値を理解し、適切な対価を支払うことができる方々も存在します。人間なので利己的な部分は誰にでもありますが、それを制御できない人はできないのです。そうなると、マジックの種を大事に扱う方々にだけ種明かしをするのが、現実的な解決策の1つになると思います。
当サイトの立場
当サイトとしては、基本的に種明かしに対しては消極的な立場です。上記のように、マジックの種明かしについての立場を見てきましたが、実際は、単純な二項対立とはならず、許容度の幅があると思います。当サイトも同様です。以下に、当サイトの種明かしに対する立場を示そうと思います。
詳細な種明かしは一般公開しない
無料公開の範囲では、演技を具体的に再現できるほど詳しい種明かしはしません。具体的には、YouTubeであれば、調べなくても関連動画に表示される可能性があるので、演技動画やテクニックの紹介にとどめます。一方、ウェブサイトの記事は、検索しなければ出てこないため、専門用語を用いて、ある程度の知識のある方には分かるように、簡単な説明をすることがあります。
種明かしは有料で行う
やはり、マジックの種明かしを無料で行うこと自体が、マジックの価値を貶める面はあると思います。マジックの種は、クリエイターの仕事の価値を理解し、それに適切な対価を支払い、秘密を守れる方だけが知っていれば十分だと考えるからです。
出典を示す
とはいえ、私のマジックに関する知識や経験は、大部分を先人の成果に依存しています。独自性や付加価値があると主張するのであれば、過去の成果物を検証し、自身の貢献した部分を明確にする必要があると考えます。一般的に知られたマジックだと主張する場合も同様です。その主張が正当かどうか、第三者が検証できるよう、出典を示すのが誠実な態度だと思います。
終わりに
マジックの種明かしはタブー視されていますが、多くの場合において、程度の問題として扱われている印象を受けました。種明かしの基準が自分と違う人はいるものですし、その基準を揃えることは困難でしょう。しかし、それぞれがどのような視点で賛否を主張しているのかを理解しておくことは大事だと思います。
私としては、自分が時間とお金をかけて手に入れ、大事に守ってきたマジックの秘密を、簡単に明かすのは気が引ける、というのが正直なところです。それに、マジシャンとして秘密を守り、観客に魔法を見せられる存在でありたいとも思います。
当サイトのコンテンツも、種明かしと言えばそうなのですが、それを閲覧できるのは、真摯で熱意のある方々だけで良いかなと考えています。簡単に種明かしを見られる場所で、マジックの種明かしを興味本位で見た人が、その種を大事に扱うとは思えないからです。そして、マジックを大事する方々の熱意に応えるべく、自身の知識や経験、参考文献の調査、映像資料などで行間を補い、コンテンツの価値を高めていきたいと考えています。
参考文献
- 「マジック種明かし番組」問題特集
http://magsting.o.oo7.jp/Exposure/exposureTop.htm
Valentino氏、緒川集人氏など、2000年代のマジックの種明かし問題が詳細にまとめられています。 ↩︎ - トランプマンのマジックワールド | マジック・ラビリンス
https://www.tokyomagic.jp/labyrinth/matsuyama/original-01.htm
法律上のマジックの扱いについて整理されています。 ↩︎ - 不思議(フシギ)とは? 意味や使い方 – コトバンク
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8D%E6%80%9D%E8%AD%B0-617975 ↩︎ - 奇術 – Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/奇術
サーストンの三原則について書かれている。日本では一般的だが、海外ではそうでもないそうです。 ↩︎ - 知的財産権について | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html ↩︎ - 特許・実用新案文献表示|J-PlatPat [JPP]
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200 ↩︎ - Teller (magician) – Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Teller_(magician) ↩︎ - 手品専用の共有サイト「AoM」を通して語られるトリックの著作権とその功罪 【後編】 | News: MAGIC MORE
http://magicmore.net/torrent-aom-conclusion/ ↩︎ - 「クリエイターの搾取やめろ」 欧州の団体がテック業界に抗議 | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)
https://forbesjapan.com/articles/detail/23819
受益者やプラットフォームの運営者が著作権者に正当な対価を支払わない状況はしばしば問題視されています。 ↩︎ - 著作物って何? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html
「頭の中にあるイメージやアイデア、あるいは技法などは著作物ではなく、作品として具体的に表現されて、はじめて著作物となり得る」そうなので、ステージアクトの振り付けなどは著作物とみなされるかもしれません。 ↩︎ - 「事件報道での『種明かし』適法」 マジシャンらの請求棄却: J-CAST ニュース【全文表示】
https://www.j-cast.com/2008/10/31029612.html?p=all
ギミックコイン制作のために貨幣を損壊した事件の報道を目的に、テレビ局が種明かしをしました。このことを不服としたマジシャンらが起こした訴訟です。 ↩︎