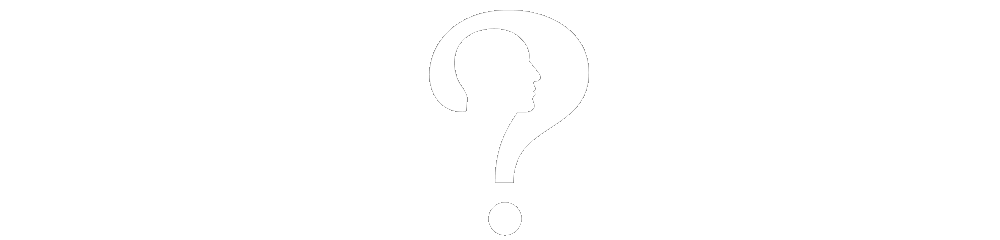マジックにも様々な種類がありますが、よく演じるマジックもあれば、知らないうちに演じなくなってしまうマジックもありますね。この記事では、どのようなマジックが使いやすく、実用的なのか、その条件について考えてみました。
使いやすいマジックの条件
現象の効果が大きい
当たり前ですが、マジックとして面白いことは大前提です。何が起こっているか分かりやすく、驚くポイントがきちんと設定されているマジックを選びます。間延びするセリフ、シャッフルやカードの記憶など、観客に負担をかける行為が多すぎると、現象が薄れてしまうので、こうした問題が無いかどうかを見直すことも大事です。
シンプルな道具
道具に仕掛けや準備が必要ない、もしくは、簡単なセットアップで使用できることは重要だと思います。トランプならばレギュラーデックで演じられる、もしくは、シャッフルした後でもすぐにセットアップできるようなトリックは重宝するでしょう。観客に認識されてはいけないギミックが増えるほど、処理について考えるための思考リソースが必要となり、演技でミスするポイントを増やしてしまいます。
実力相応のテクニック
とはいえ、全て高度なテクニックで演じる作品のが良いのか、というと、そうとも限りません。テクニックに依存するマジックは、高度なテクニックであるほど、繊細な動きが要求されるため、その時のコンディションの影響を受けやすいです。同時に、難しい技術をすぐ使えるようにするために、それを普段から維持することが求められます。ですので、テクニックの引き出しを増やす取り組みは続けながらも、実際に演じる場合は、確実に習得した完成度の高いテクニックで演技を組み立てていくのが良いと思います。
思考リソースを使わない
演技の進み方に応じて、アドリブを入れたり、ミスを修正したりする必要があるため、可能な限り、頭が回転する余力を残して演技したいところです。ルーティーンの長さは長すぎず、適度な長さに留める必要があります。アウトなどを記憶する場合も、できるだけパターンを減らす工夫をしたいところです。記憶することが多い場合は、カンニングペーパーを用意するなどすると、負荷を軽減できます。
制約が小さい
演じる際の角度、観客との距離、服装、明るさなど、細かな制約が付くマジックも、演じやすいとは言えません。手渡しできない道具も1つの制約でしょう。求められなければ、手渡しで改める必要は無いですが、手渡しできない道具を使うと、常に改めを求められた場合の対応を考えなくてはならなくなります。演じる機会が多いほど上達しますし、どのような機会でも演じられるようなマジックが良いですね。
終わりに
以上、使いやすく、実用的なマジックの条件について考えてみました。
マジシャンにとっても観客にとっても、できるだけ負担が小さく、それでいて効果が大きいマジックが良いと考えています。
私も過去に、デックの並びを全て暗記するようなマジックも考えたのですが、演じるのが面倒でやらなくなってしまいました。手間のかかる演技は、マニア向けだと思います。
このサイトでは、実用的かどうかによらず、面白そうだと感じたアイディアはできるだけ共有していきます。一方、実際に手順を組むときには、何度でも演じたくなるようなマジックになっているかという視点も持ちたいところです。